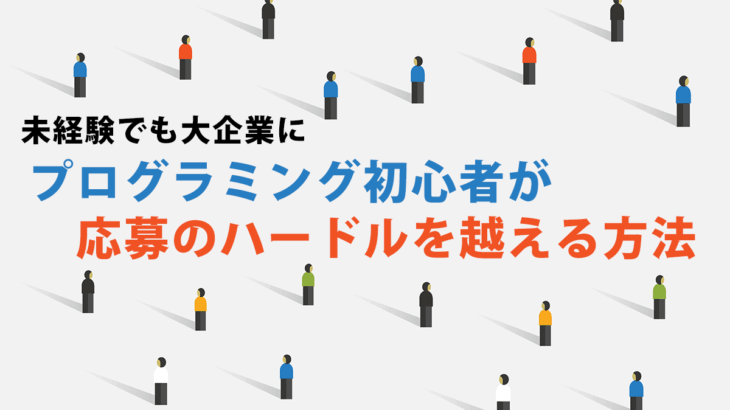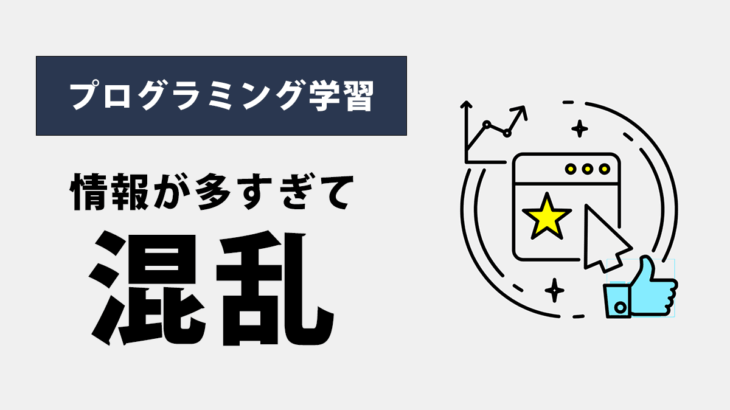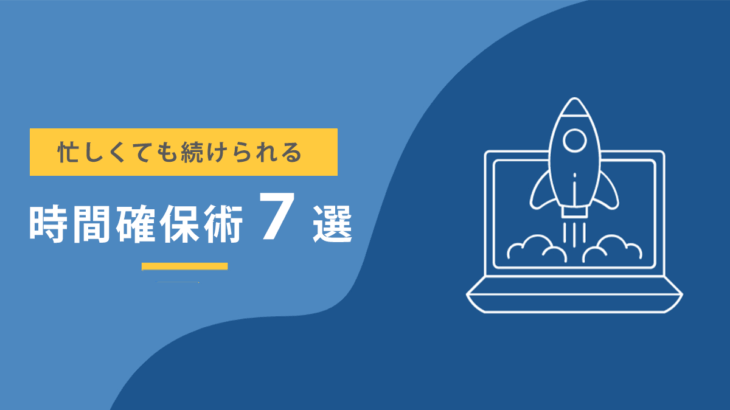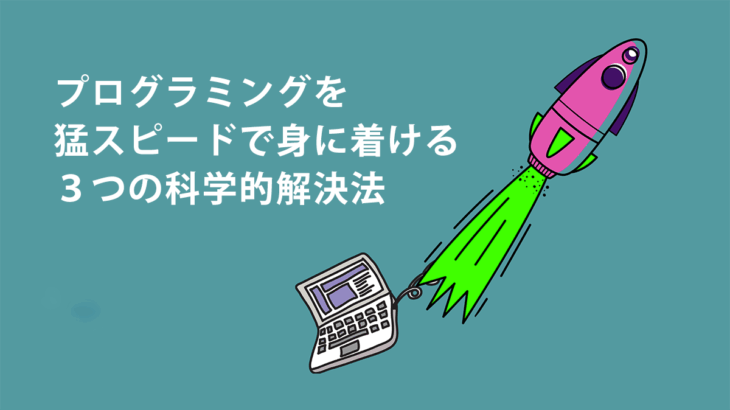こんにちは!かたやまです。
プログラミングを学び始めたあなた、こんな壁にぶつかっていませんか?
「いいなと思った求人、見てみたら『実務経験3年以上』って…まだ勉強始めたばかりなのに!」
よくわかります。求人サイトを見るたびに「実務経験○年以上」という文字が目に飛び込んでくると、本当に心が折れそうになりますよね。
でも、実はここに大きな誤解があるんです。実務経験が必要な求人だけが、すべてじゃありません。
今日は、未経験者がどうやって応募のハードルを越えていけばいいのか、科学的な根拠も交えながら、具体的な方法をお伝えします。
なぜ企業は「実務経験」を求めるのか?
まず、相手の立場で考えてみましょう。企業が「実務経験3年以上」と書くのには、理由があります。
それは**「すぐに戦力になってほしい」**という願いから。
これは、あなたが友達に荷物の運搬を頼むときを想像してみてください。急いでいるときは、力持ちで慣れている友達に頼みますよね。でも、時間に余裕があるなら、「まだ慣れていないけど、これから一緒に成長していこう」という友達を選ぶこともあるはず。
企業も同じです。余裕があるときは、未経験者を育てる選択肢を持っているんです。
実は増えている!「ポテンシャル採用」という新しい流れ
近年、IT業界では「ポテンシャル採用」という言葉が注目されています。
これは、今持っているスキルよりも**「将来の可能性」や「学ぶ意欲」を重視する採用方法**のこと。
リクルートの調査によれば、2022年度の転職では「異業種×異職種」への転職が全体の約4割を占め、過去最多となりました。つまり、未経験からのキャリアチェンジが当たり前の時代になってきているんです。
ポテンシャル採用が注目される理由
- 労働人口の減少: 即戦力だけでは人材確保が追いつかない
- IT人材の不足: エンジニアの求人倍率は7.10倍(doda調べ、2025年2月)と、全体平均の2.46倍を大きく上回る
- 育成コストの低下: 第二新卒など、基本的なビジネスマナーが身についている若手は、新卒よりも育成しやすい
これらの背景から、大企業でも未経験者採用に積極的になってきているのが現状です。
未経験歓迎の大企業、実はこんなにある!
「大企業は経験者ばかり採用してる」と思っていませんか?
実は、以下のような大企業が未経験者やポテンシャル採用を実施しています:
IT業界の大手企業
- NTTデータ: 「IT未経験×第二新卒」の座談会を公式開催するなど、未経験者採用に積極的
- 富士通: 2022年6月から通年採用を実施し、柔軟な採用スタイルを確立
- 日立製作所: 手厚い研修制度で、未経験でも基礎から学べる環境
- NEC: 第二新卒やポテンシャル採用の枠を設けている
その他の業界
- イオングループ: 複数社を併願できる合同募集で、未経験者も応募しやすい
- 楽天: 新卒・第二新卒採用に力を入れており、研修制度が充実
これらの企業は、「今のスキル」よりも「これからの成長」を見てくれるんです。
科学的根拠:未経験者が成功する3つの理由
「未経験でも本当に大丈夫?」という不安、よくわかります。
でも安心してください。未経験者が活躍できることには、しっかりとした理由があるんです。
1. 柔軟性の高さ(神経可塑性)
脳科学の研究では、大人になっても脳は新しいことを学び、変化し続けることが証明されています(神経可塑性)。
特に20代は、前職の働き方に染まりきっていないため、新しい環境に順応しやすい。これは、まっさらなスポンジが水を吸収しやすいのと同じイメージです。
2. 成長意欲の強さ
ポテンシャル採用に応募する人は、自ら学び、キャリアを変えようとする主体性を持っています。
この「学習意欲」は、スキルそのものよりも重要な資質。リクルートが実施した人材育成の研究でも、学習意欲の高さが長期的な成長につながることが示されています。
3. 育成効果の実証
厚生労働省の調査や複数の人材育成研究によれば、体系的な育成プログラムがあれば、未経験者でも十分に戦力になることが実証されています。
大切なのは「今のスキル」ではなく、「学ぶ姿勢」と「適切なサポート」なんです。
応募のハードルを越える5つの実践ステップ
では、具体的にどうすればいいのか。5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:「未経験歓迎」「ポテンシャル採用」を狙う
まずは、求人の探し方を変えましょう。
検索キーワードに以下を含めてみてください:
- 「未経験歓迎」
- 「第二新卒」
- 「ポテンシャル採用」
- 「研修制度充実」
これだけで、見える世界がガラッと変わります。
おすすめの転職エージェント:
- ワークポート: IT未経験者のサポートに強い
- マイナビIT AGENT: 未経験のアピール方法を教えてくれる
- ハタラクティブ: 第二新卒・既卒に特化
ステップ2:自主学習の「証拠」を作る
「未経験歓迎」といっても、完全にゼロの状態より、少しでも学んでいる姿勢を見せることが大切です。
これは、レストランで「料理未経験歓迎」とあっても、家で少し料理を練習している人の方が採用されやすいのと同じ。
具体的にやること:
- オンライン学習サービス(Progateなど)の学習履歴
- GitHubにポートフォリオを公開
- Qiitaなどで学習記録を発信
- 資格取得(ITパスポート、基本情報技術者試験など)
ステップ3:転職理由を明確にする
「なぜプログラミングを学びたいのか?」 「なぜこの会社で働きたいのか?」
この2つに明確に答えられるようにしましょう。
良い例: 「御社の〇〇というサービスに感銘を受け、自分もユーザーの課題を解決するシステムを作りたいと思いました。独学で基礎を学びましたが、プロの環境で実務を通じて成長したいと考えています」
NG例: 「プログラミングが流行っているので」 「給料が良さそうだから」
ステップ4:「学ぶ姿勢」を全面に出す
面接では、「今のスキル」ではなく「学ぶ姿勢」をアピールしましょう。
効果的なアピール方法:
- 具体的な学習時間を伝える(「毎日2時間、3ヶ月間継続しました」)
- 困難を乗り越えた経験を語る(「エラーが出たときに、3日かけて解決しました」)
- 質問する(「入社後の研修制度について教えてください」)
ステップ5:複数社に並行応募する
これが最も重要です。
1社だけに絞ると、不採用になったときのダメージが大きすぎます。
野球選手が打率3割で一流と言われるように、転職活動も「何回挑戦したか」が大切。最低でも5〜10社は並行して応募しましょう。
これは「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」ではなく、**「チャンスを最大化する戦略」**です。
よくある質問と回答
Q: 年齢的に未経験は厳しいでしょうか?
A: ポテンシャル採用の対象は一般的に20代が中心ですが、30代でも可能性はあります。ただし、30代は20代よりもさらに「学習実績」と「明確な志望動機」が求められます。
Q: 学歴がないと難しいですか?
A: 大企業の場合、学歴を重視する傾向はありますが、絶対条件ではありません。むしろ、ポートフォリオや学習姿勢で勝負しましょう。実際、学歴よりも「何を作ったか」を見る企業も増えています。
Q: プログラミングスクールは行くべき?
A: 絶対ではありませんが、企業紹介がセットになっているスクールは、未経験者の就職ルートとして効果的です。ただし、高額なので慎重に選びましょう。
筆者の考え:新技術は「全員スタートライン」のチャンス
ここで、私自身の経験からお伝えしたいことがあります。
最近のIT業界は、新しい技術がものすごいスピードで出てきています。
生成AI、Web3、クラウドネイティブ、ノーコード/ローコード…数年前には存在しなかった技術が、今や主流になりつつあります。
これ、何を意味するかわかりますか?
みんなが初心者からスタートする技術が、今この瞬間も生まれ続けているということです。
例えば、2022年末にChatGPTが登場したとき、世界中のエンジニアが「ゼロ」から学び始めました。ベテランも新人も関係なく、全員が同じスタートラインに立ったんです。
つまり、新技術の分野では:
- 実績を持つ人がまだ少ない
- 「実務経験3年以上」という条件そのものが存在しない
- 未経験であることが、ハンデにならない
むしろ、情報感度が高く、新しいことを学ぶ意欲がある人なら、早めにキャッチアップすることで、ベテランより優位に立つことさえできるんです。
実際、私が見てきた中でも、新技術の波に乗って一気にキャリアアップした人は何人もいます。
変化の激しい時代だからこそ、「今はまだ初心者」という状態は、実は大きなチャンスでもあるんです。
まとめ
「実務経験〇年以上」という文字を見て諦めていたあなたへ。
実は、その壁は思っているほど高くありません。
大切なのは3つ:
- 「未経験歓迎」「ポテンシャル採用」の求人を探すこと
- 学ぶ姿勢と実績を見せること
- 諦めずに複数社にチャレンジすること
IT業界は慢性的に人材不足で、企業も「育てる前提」で採用を考えています。今は、未経験者にとって過去最高のチャンスなんです。
次の一歩
今日から始められることがあります:
- 今日: 転職エージェント(ワークポート、マイナビIT AGENTなど)に登録する
- 今週: 学習履歴をまとめ、GitHubアカウントを作る
- 今月: 3つ以上の「未経験歓迎」求人に応募する
未来のあなたが、大企業でエンジニアとして活躍している姿を想像してみてください。
その第一歩は、今日のあなたの行動から始まります。
応援しています!
参考文献・出典
- 株式会社リクルート「異業種×異職種転職が全体のおよそ4割」(2023年11月)
- doda「転職求人倍率レポート」(2025年2月)
- リクルートエージェント「ポテンシャル採用の導入と効果」(2024年)
- 総務省統計局「人口推計」(2023年)
- 法政大学 佐藤厚「企業における人材育成の現状と課題」
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」関連資料
※本記事の内容は2025年10月時点の情報に基づいています